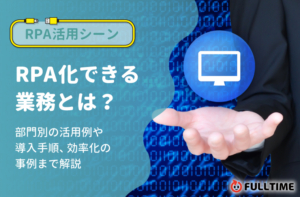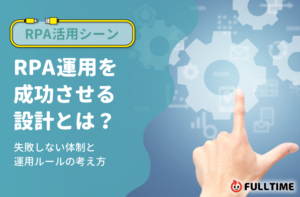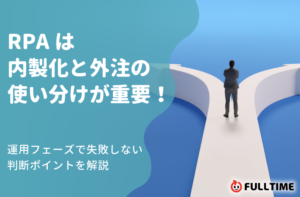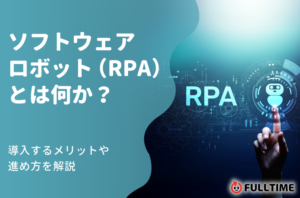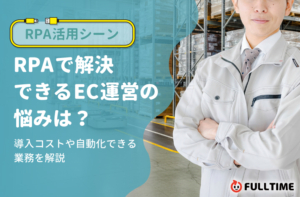RPAの要件定義とは?導入による業務効率化を成功させるポイントも解説

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、定型的な業務を自動で処理してくれる便利なツールですが、ただ導入すれば自動的に業務が改善されるわけではありません。
成果を出すには、「どの業務をどのような理由で、どのように自動化するか」を事前に整理・設計する要件定義の精度が重要になります。
しかし「RPAの要件定義がよく分からない」「自社の業務に向いているのか分からない」といった、疑問や不安から導入に踏み切れずにいる企業の担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、RPAの要件定義から開発手順まで詳しく解説しています。
- 【本記事で分かること】
※タップで該当箇所へスクロールします。 - RPAの要件定義とは
- RPA要件定義の開発手順
- RPA要件定義を成功させるためのポイントと注意点
RPA導入を成功させるためのポイントと注意点も紹介していますので、ぜひ参考にして自社に最適な業務の自動化や効率化の一歩を踏み出しましょう。

EC特化型RPAツール「FULLTIME」なら、面倒な作業をまるごと自動化が可能です。
- 導入前・導入後もRPAコンサルタントがしっかりサポート
- 要件定義〜構築〜保守まで丸ごと対応
- 課題に合わせたRPAを構築
- 受注・出荷・顧客対応などのテンプレートが豊富
- 外部のツールやシステムとの連携が可能
要件定義から設計・開発・保守までをワンストップで提供しており、RPAに不慣れな企業でもスムーズに導入・運用できます。
カスタマイズや外部ツールとの連携も可能で主要なECシステムはもちろん、さまざまなシステム環境にも柔軟に対応できます。
- 要件定義を外部に依頼したい
- 本来やるべき仕事に専念したい
- 少人数でEC運営をしている
- 手作業による人的ミスを減らしたい
- 複数のシステムや外部ツールと連携させたい
面倒な手作業や人為的ミスから解放されて、本来のやるべき業務に集中する環境を作りませんか?
FULLTIMEを実際に導入された企業様の事例やお役立ち情報も紹介していますので、まずは以下からご確認ください。
\EC業務をもっと効率的に!/
RPAの要件定義とは|業務自動化の範囲と適切なツール選定を行うプロセス

RPAの要件定義とは自動化すべき業務の内容や範囲を明確にし、目的に適したツールや機能を選定するための「設計図」を作成するプロセスです。
この段階で業務内容を正確に把握し、必要な機能や品質要件を整理できれば、RPA導入による成果を最大化できます。
またRPAにおける要件定義は、大きく「機能要件」と「非機能要件」に分類されます。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 機能要件 | ▼定義 ロボットが実行すべき具体的な処理内容 ▼具体例 ・データの取得・更新・削除 ・自動でのメール送信 ・ユーザーのログイン認証など |
| 非機能要件 | ▼定義 システムの性能や品質に関する要件 ▼具体例 ・処理速度 ・セキュリティ ・稼働率 ・操作性など |
たとえば、ECサイトの受注処理を自動化する場合、注文情報の取得が機能要件です。
一方で、「1時間に100件の処理速度」や「99.9%の稼働率」といった性能や信頼性に関する数値指標は非機能要件に分類されます。
このように、機能要件は何をするか・非機能要件はどのように実行されるかを定めます。
要件定義が不十分なまま導入を進めると、以下のような問題が発生する可能性もあります。
- 処理速度が遅くなる
- 操作が複雑になる
- セキュリティリスクが甘くなりトラブルが発生しやすくなる
- 本来解決したかったことができない
- エラー率が高くなる
こうした失敗を防ぐには、業務現場の声と技術的要件の両方を取り入れ、機能要件・非機能要件をバランスよく定義することが重要です。
RPAのツールの選定や設計の前に、「何を、どこまで、どのように自動化すべきか」を、業務部門とIT部門が連携して定めることが、プロジェクト成功の第一歩となります。
要求定義との違い
RPA導入において要件定義と混同されやすいのが、「要求定義」です。
両者は似た言葉ですが、以下のように意味合いと役割が明確に異なります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 要求定義 | 業務担当者や現場からの「こうしたい」「こうあってほしい」というニーズや期待値を整理・明文化するプロセス 例:エラー対応を自動化したい/毎朝の在庫集計をロボットに任せたいなど |
| 要件定義 | 要求定義をもとに、それを実現するために必要なシステム仕様・機能・操作フローを具体化する設計工程 例:エラー検知後は○○システムにログを残し、担当者にメール通知を行うなど |
要求定義は「こうしたい」という要望やニーズを整理するプロセスに対して、要件定義は「どう実現するか」を具体的に落とし込むプロセスを指します。
要求が不明確なまま要件を詰めてしまうと、実装後に「思っていたものと違った」といったギャップが生じやすくなるため、段階を追った設計が重要です。
RPA導入する際には、まず何を自動化したいのか(要求)を明確にし、次にどう設計するか(要件)を段階的に詰めていくことが成功のポイントです。
要件を決めずにRPAを導入すると業務が複雑化するリスクも
RPAをスピード優先で導入し、要件定義を省略すると以下のように業務全体へ深刻な支障をきたす恐れがあります。
| リスクの種類 | 発生する問題例 |
|---|---|
| 自動化対象の選定不足 | 手作業との連携が乱れ、作業時間が増加する |
| ツール選定のミス | ・不要なコスト増加 ・システム管理・運用が煩雑になる |
| 現場ニーズの反映不足 | ・現場で活用されず、定着率が低下する ・運用時に混乱が生じる |
| 例外対応の設計不足 | ・想定外のケースでロボットが停止する ・手作業での対応が頻発する |
| 業務分担の曖昧化 | 作業範囲が不明確となり、対応漏れ・重複・責任の所在不明が発生する |
| 要件定義の未整備 | ・メンテナンスが困難になり属人化する ・仕様変更時に大幅な工数がかかる |
例えば、業務フロー全体を見渡さずに一部だけを自動化すると、前後工程で手作業の調整が必要になり、かえって業務が煩雑になるリスクがあります。
また高機能なRPAツールを導入しても、実際に利用する機能が限られていると不要なコストや管理負担が発生する原因になります。
現場の実態が反映されていないと、仕様と運用にギャップが生じ、現場での運用が定着せず、ツールが機能しなくなる恐れがあります。
このようなリスクを回避するには、以下を徹底することが重要です。
- 業務全体のプロセスを可視化し、自動化の範囲と優先順位を明確化
- 自動化と人の役割を区別し、責任範囲を明文化
- 関係者全体での認識共有と合意形成
これらを押さえた上で要件定義を行うことで、スムーズな導入と安定した運用につながります。
RPAに向かない業務の特徴
RPAに向かない業務の特徴は、以下の通りです。
- 判断・思考・例外対応が頻発する業務
- ルールが曖昧/頻繁に変更される業務
- 手書き書類や画像から情報を読み取る業務
- 担当者によって処理内容が異なる業務
このような業務を無理に自動化しようとすると、ロボットの設計が複雑化し、導入後に頻繁なエラーやメンテナンスが発生し、かえって非効率になる可能性があります。
「どの業務をどう自動化すべきか」を見極めるために要件定義を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- RPAに適した業務と不向きな業務を切り分けられる
- 後工程(ロボット設計・開発)での手戻りを防げる
- 自社に最適なRPAツールの選定がしやすくなる
社内にRPAや業務自動化の知見がない場合は、外部パートナーの力を借りて要件定義を進めるのも有効です。
FULLTIMEでは、RPA導入前の業務整理や要件定義から実装・運用支援までワンストップでサポートしています。
初めてのRPA導入でも、安心してご相談ください。
\ まだまだたくさん!導入事例あります! /
RPA要件定義の開発手順|現場の業務フロー確認が大切

PRA要件定義の開発手順は、以下のとおりです。
| 手順 | 実施内容 | 成果物 |
|---|---|---|
| 1.対象業務選定 | 自動化効果が高い業務を優先 | 自動化優先順位表 |
| 2.業務可視化 | フローチャート作成 | 現行業務フロー図 |
| 3.運用整理 | 権限/責任範囲の明確化 | 運用ルールブック |
| 4.定義書作成 | 要件の文書化 | 要件定義書 |
開発する際は、現場の業務フローを細部まで確認する必要があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
対象業務の選定と目標設定
RPA導入を成功させるには、自動化する業務の選定と自動化によって達成したい目標の明確化が不可欠です。
一般的に作業の繰り返しが多く、ルールが明確で処理件数が多い以下のような業務が自動化に向いています。
- データ入力や集計
- 定型的なメール送信
- システム間のデータ転記
こうした業務を洗い出すためには、現場担当者へのヒアリングや、作業内容・頻度・所要時間の棚卸しを行うことが重要です。
また自動化によってどの程度の効率化やコスト削減が期待できるかを、定量的・定性的に分析していきます。
単に手間がかかる業務に着目するのではなく、どれだけ効果が見込めるかという視点で優先順位を判断することが重要です。
現状の業務プロセスの可視化
RPA導入の準備段階で欠かせないのが、現状の業務プロセスを可視化する作業です。
これにより、どの業務が自動化に適しているのかを正確に把握できます。
業務プロセスの可視化は作業の流れを図示するだけではなく、以下のような全体像が分かるようになります。
- 各工程で発生している作業内容
- 入力データ
- 関与する担当者
- 使用しているシステムや帳票の細かい洗い出しなど
この工程を進めると、無駄な手戻りや重複作業が発生していないかを客観的に評価が可能です。
例えば、フローチャートや業務マニュアルを作成し、現場担当者と確認を行いながら整理することで、実態に即した情報を高い精度で収集できます。
現状の流れを正確に捉え、改善点と自動化の余地を見極めることで導入後の運用がスムーズになり、ROI(投資対効果)の最大化にもつながります。
運用に関する情報を整理する
RPAを導入して業務を自動化する際は、安定したシステム稼働とトラブル発生時の迅速な対応を徹底しなければいけません。
その上で鍵を握るのが、以下のような運用に関する情報をあらかじめ整理・明文化しておくことです。
- 運用手順の明確化
- リソースの可視化
- 担当者の責任範囲
- 管理方法の設計
これらの情報整理を怠ると、以下のような運用上のトラブルが発生しやすくなります。
- エラー発生時の対応が遅れる
- 運用ルールが現場に浸透しない
- メンテナンスや改善作業が属人化する
RPAがどのタイミングで起動し、どの業務をどの順序で処理するかを明文化しておき、定期的なメンテナンス作業やエラー発生時の対応フローも具体的に記載することが重要です。
これらの情報を事前に整理・共有・文書化しておくことで、RPA導入後もスムーズな運用が可能になります。
要件定義書の作成
RPAの要件定義書とは、業務の自動化を成功させるために「何をどのように自動化するか」「ロボットがどのように動作するか」を文書で明確に示す導入の設計図です。
記述すべき項目とポイントは、以下のとおりです。
| 項目 | 内容の例・ポイント |
|---|---|
| 目的・背景 | なぜRPAを導入するのか、解決したい課題や目標を明記 |
| RPAツールやシステムに関連する制約条件 | 使用ソフト・インフラ・予算・スケジュールなどの前提条件 |
| 対象業務の可視化 | 自動化する業務の流れやフロー図、現状の課題を整理 |
| 運用要件 | ロボットの動作条件、運用手順、担当者や管理体制を明確化 |
| 機能要件 | ロボットが実行する具体的な動きや処理内容を細かく記載 |
| データフロー図 | データの流れを図で整理し、どこで何を処理するかを明確化 |
| レビュー・合意 | 関係者で内容を確認し、認識のズレがないかをチェック |
ロボットの動作や処理内容(機能要件)に加えて、処理速度やセキュリティなどの品質条件(非機能要件)も明記することで、導入後のトラブルや運用負荷の発生を未然に防げます。
またエラー発生時の対応フローを事前に明記しておくことも重要で、突発的な事象にも迅速に対応できる体制が整い、業務の安定稼働につながります。
要件定義書の完成後は関係者全員で内容をレビューし、認識にズレがないかを確認するプロセスを必ず設けましょう。
このようにRPA導入を成功させるためには、要件定義書を丁寧に作成し、現場の実態とすり合わせながら仕様を固めていくことが不可欠です。
RPA要件定義を成功させるためのポイントと注意点
RPAの要件定義を成功に導くには、以下のポイントと注意点を押さえておく必要があります。
| 注意点 | ポイント |
|---|---|
| 業務プロセスの理解 | 現行業務を正確に把握し、自動化に適した業務を選定する |
| 目標と成果の明確化 | 目的と成果を数値で定義し、関係者と共有する |
| 機能と非機能要件のバランス | 機能面だけでなく、処理速度・セキュリティ・操作性など品質面も考慮 |
| ステークホルダーとの合意形成 | 各部門と密に連携し、認識のズレを防ぐ |
| 継続的な改善 | 運用開始後も定期的に見直し、現場の声を反映する |
業務フローを可視化し、繰り返し作業やルールが明確な業務など、自動化に適した対象を見極めることがRPA導入の基本です。
導入の目的と成果を明確にし、「月間作業時間を30%削減」など具体的な数値目標を関係者全員で共有することで、プロジェクトの方向性がぶれず、効果測定も簡単になります。
このように、要件定義の段階で「何を」「どこまで」「どのように」自動化するのかを明確にし、関係者と合意形成を図ることで、RPA導入後のトラブルを防ぐことができます。
要件定義を活かしてRPA導入に成功した事例|EC業務を効率化したFULLTIMEの活用例
要件定義を活かして、RPA導入を成功させた事例は数多くあります。
一例として、株式会社未来様は「FULLTIME」を利用し、人力で対応すると半日ほどかかっていた複雑な業務フローやイレギュラーな処理の自動化に成功しました。
「FULLTIME」は、EC事業者が日々直面する煩雑な業務を効率化するRPAツールです。
注文確認やお届けサイクルの変更、返品リスト管理など、ルールベースで繰り返される作業を幅広くカバーします。
ロボットは24時間365日稼働するため、連休中や夜間でも業務を止めることなく処理を継続でき、ヒューマンエラーの削減や現場スタッフの負担軽減にもつながります。
FULLTIMEの詳しい導入効果や運用フローについて知りたい方は、以下の事例紹介ページもぜひご覧ください。
\ まだまだたくさん!導入事例あります! /
RPA要件定義に関するよくある質問と回答
RPA要件定義に関するよくある質問と回答は、以下のとおりです。
RPA導入を検討されている方は、ぜひ参考にして不安や疑問を事前に解消しましょう。
RPAを導入する前提条件は?
RPA導入の前提条件は、以下のとおりです。
- 自動化する業務がパソコン上で完結する
- 定期的に発生する
- ルールが明確で再現性がある
このように繰り返しが多く、手順が標準化されている業務はRPAに適しています。
加えて、現状の業務プロセスを分析し、どこに非効率やミスが多いかを把握する必要があります。
IT環境や既存システムとの互換性も確認し、導入するツールが自社の業務やシステムに適合するか検討しましょう。
これらを満たせば、RPAによる業務効率を最大化できます。
要件定義と機能要件との違いは?
要件定義と機能要件との違いは、以下の通りです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 要件定義 | ・プロジェクト全体の設計図 ・自動化の目的や背景を明確化 ・対象業務の範囲・優先順位を整理 ・必要な機能・運用条件を文書化 ・機能要件・非機能要件の両方を含む ・関係者との合意形成にも使われる |
| 機能要件 | :要件定義の一部 ・RPAが「何をするか」を明記(処理内容や手順) ・具体的な動作の流れを記述 ・UIの操作手順や連携するシステムを含む ・非機能要件は含まない |
要件定義はRPAで自動化したい業務や達成したい目標、必要な機能や運用条件など、全体像を整理し文書化するプロセスです。
一方で、機能要件はRPAが実際にどのような作業を行うか、どんな動きをすべきかを具体的に記載します。
つまり、要件定義はプロジェクト全体の設計図であり、機能要件はその設計図の中でRPAが担う動作や処理内容を細かく定めたものです。
要件定義には非機能要件(セキュリティや操作性など)も含まれますが、機能要件は「何をするか」に特化しています。
RPAの要件定義にかかる期間の目安は?
RPAの要件定義にかかる期間は、2週間から1ヶ月ほどとされています。
小規模な業務やプロセスであれば2週間ほどで完了しますが、複数部門にまたがる全社的な導入や、複雑な業務フローの場合はさらに時間がかかります。
要件定義では、以下の準備が欠かせません。
- 業務の選定
- 業務の評価
- 現場ヒアリング
- 要件の文書化
- 関係者との合意形成
期間を短縮しすぎると、これらの準備がおろそかになるため、トラブルや手戻りが生じやすいです。
RPAの要件定義は余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
RPA導入は精度の高い要件定義が重要!プロに任せて業務効率化を成功させよう
RPA導入を成功させる上で、最も重要なのが精度の高い要件定義です。
どの業務をどう自動化するかが曖昧なまま進めてしまうと、かえって業務が複雑化し、期待した効果を得られません。
また、RPAは手順が明確な定型業務に強みを持つ一方で、人の判断や例外処理が多い業務には適しておらず、パソコン上で完結する作業を見極めて選定する必要があります。
このように要件定義から自動化設計までを自社で完結させるのが難しい場合は、専門サービスの活用が効果的です。
RPAツールの「FULLTIME」では、業務の棚卸しから運用支援まで、現場に寄り添った一貫対応を行っています。
| FULLTIMEのメリット | 内容 |
|---|---|
| 業務時間の削減 | 受注処理や顧客対応を自動化し、最大90%の工数を削減 |
| 残業・負担の軽減 | 単純作業をロボットに任せ、社員は本来の業務に集中できる |
| ミスの減少・品質の向上 | 入力ミスやチェック漏れが減り、顧客満足度も向上 |
| 24時間365日稼働 | 夜間や休日も処理が止まらず、対応の遅延を防止 |
| 柔軟な業務拡張・自動化範囲の拡大 | 自動化対象を追加し、導入後も継続的な効率化が可能 |
| ストレスの軽減・働きやすい環境 | ルーティン作業から解放される |
| 安心のサポート体制 | 導入後もトラブルに迅速対応。現場が安心して使える |
正確な要件定義と専門的な支援が揃えば、RPAの導入効果を最大化できます。
RPA導入をご検討中の企業様は、ぜひ「FULLTIME」へお気軽にご相談ください。
\ まだまだたくさん!導入事例あります! /